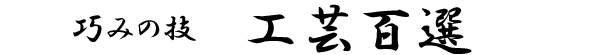業種別一覧表
陶磁器
 九谷焼
九谷焼
日用品から高級品まで、和食に限らず、フレンチなどの洋食との組み合わせもお薦めです。
加賀百万石の伝統を受け継ぐ色絵陶磁器、九谷焼。 三助焼
三助焼
150年の伝統、地元で取れる土と、その土地が生み出した草木から釉薬を作り、すべての工程を手作業で。淡く深い緑色の釉薬が特徴。 越前焼
越前焼
「越前焼き」は平安末期から続く日本六古窯の一つ。
特徴は鉄分を多く含むため耐火度が高く、茶褐色な焼き上がり。 能登大社焼
能登大社焼
昭和23年、能登半島羽咋市の能登一の宮、気多大社に隣接した地に開釜。周辺の土を使い、生の葉を焼き付けた、独自の『真葉手(しんようで)』という陶磁器を制作。 一葉窯
一葉窯
"木の葉天目"とは木の葉の灰を釉薬に転用することで木の葉模様を焼き付けるもの。
お酒を入れると浮き上がって見えてくる木の葉の感じをお楽しみ下さい。
漆器
 高岡漆器
高岡漆器
高岡漆器は、江戸時代の初めに、加賀藩の藩主前田利長が、現在の富山県高岡市に高岡城を築いたとき、武具や箪笥、膳等日常生活品を作らせたのが始まり。
高岡の祭で使われる絢爛豪華な御車山(みくるまやま)にこれら漆器の技が集められています。 輪島塗(田谷漆器店)
輪島塗(田谷漆器店)
重要無形文化財として、世界でもその名が知られる輪島塗。
100以上にも及ぶ工程は職人たちの分業によって成り立ち、大勢の手によって仕上げられている。 輪島塗(東野蒔絵工房)
輪島塗(東野蒔絵工房)
蒔絵師の作品の販売。
日展会友・日工会会員の蒔絵師、東野定治の作品。 山中漆器
山中漆器
山中漆器は、16世紀の後半に現在の加賀市山中温泉(石川県)に木地師集団が移住したことに始まる。漆器には、木地・塗り・蒔絵の工程があり、塗り工程はさらに下地と上塗りにわかれる。石川県には3つの漆器産地があるが、それぞれ特徴があり「木地の山中」「塗りの輪島」「蒔絵の金沢」と称されている。 越前漆器([atakaya])
越前漆器([atakaya])
シンプルなデザインがお料理をイメージアップする、漆器の新しい魅力を提案している越前漆器。普段使いの漆器から贈答用まで。
銅器
 高岡銅器(織田幸銅器)
高岡銅器(織田幸銅器)
高岡銅器は、銅合金による鋳造技術から作られ、原型づくり→鋳造→仕上げ加工→着色という工程をたどり、どの工程においても、熟練した職人が手技の粋を発揮し、それらが連携することにより1つの造形美が生まれます。 高岡銅器(小菊製作所)
高岡銅器(小菊製作所)
■玉風 水思想において蛇は大地を司る龍の化身といわれており、頭に持つ宝珠の玉の神通力で地中から宝石や貴金属を生み出すことから、蛇は「財」を表すとし繁栄の象徴とされています。
■クローバー 大地を司る蛇の像は木の下に祀ると幸福が訪れるといわれることから、木を意味する四葉のクローバーを頭上に添えてあります。
彫刻
 井波彫刻
井波彫刻
井波は全国でほぼ唯一の彫刻産地であり、経済産業大臣指定の伝統的工芸品産地である。
荒彫りから仕上げまで200本以上のノミや彫刻刀を駆使する高度な技は現在も、欄間、衝立、パネル、置物などの制作に受け継がれている。
錫製品
 高岡の錫(能作)
高岡の錫(能作)
純度100%にこだわる能作の錫は、非常に柔らかく、その特性を生かし好みの形に変えることができる。高岡の伝統工芸。 高岡の錫(木型工房HANANO)
高岡の錫(木型工房HANANO)
錫「すず」は、日本で古くから飲食器や茶壺などに用いられている金属で、外観が美しく比較的やわらかいため、女性の方でも簡単にお好みの形に整えることができます。錫製の枝部分をお好きな形に整えて、自分だけのイメージで楽しむ事ができます。
家紋商品
 美川刺繍
美川刺繍
明治23年に教師を招き、子女にハンカチ刺繍を教授したのが起こり。その後、『加賀刺繍』として、平成3年に国の伝統工芸品の指定を受ける。
磁器
 九谷和グラス
九谷和グラス
グッドデザイン賞受賞
九谷焼と江戸硝子の融合を最大の特長とする九谷和グラスは、商品の要となる接合部分の品質にも研究を重ね、接合強度を母材破壊レベルにまで高めました。
これにより2006年度グッドデザイン賞(新領域デザイン部門)を受賞しています。 エズラグラススタジオ
エズラグラススタジオ
1つ1つ手作りのこだわりグラス。世界にひとつだけのオリジナルグラス。
現在、山野宏の作品制作、工房オリジナル製品、吹きガラス講座、1日体験、ワークショップ等ガラス工芸にかかわる様々な分野で活動を展開中。世界でも有数のガラス工房。
和紙
 五箇山和紙
五箇山和紙
世界遺産五箇山の「五箇山和紙」は、江戸時代加賀藩の手厚い保護を受けながら発展し、良質和紙の産地として今日に至っています。 平成5年には、和紙でつくられた置物が、お年玉年賀記念切手のモデルとなり、全国の人々に親しまれました。
木製品・工芸品
 小浜若狭塗箸
小浜若狭塗箸
若狭塗は小浜藩の御用塗師が支那漆器の一種存星をヒントに、海底の様子を意匠化して考え出したのがはじまり。貝殻や卵殻を漆の中に埋め込んだスタイルは、若狭塗独自。 庄川木工芸品
庄川木工芸品
庄川挽物木地は横木を加工するので、道管が器に平行に走り年輪が様々な形で表れる特徴がある。使いこむほど、光沢や色調の変化が出てくる。 立山かんじき
立山かんじき
立山かんじき(和かんじき)は、古くから立山登山口の地、雪深い芦峅寺でつくられ、雪上歩行用に冬の生活必需品となっている。「丈夫」「履きやすい」「美しい」という特徴を守り通しています。
ろうそく
 能登和ろうそく
能登和ろうそく
一本一本に手描きで描いた和ろうそく。温かく優しい光を灯します。
最後まできれいに燃え尽きるのが特長。
チタン製
 福井かつき箸
福井かつき箸
「チタン」は医療用具に用いられている、金属アレルギーや環境ホルモンの心配の少ない、安全・無害な素材です。また、軽くて強く錆びないといった特性を持っており、様々な分野で利用されている、私達の生活に身近な金属です。
油彩画
 谷道 淳一
谷道 淳一
1953年 富山県新湊市に生まれる。
ゴルフコース油彩画多数。
肖像画(人物・ペット)・水墨似顔絵の制作承ります。
珪藻土
 能登珪藻土(けいそうど)
能登珪藻土(けいそうど)
能登の珪藻土(けいそうど)---
海水に生じる植物性プランクトン「珪藻」の殻がそのまま海底に沈み、堆積して出来た土のこと。奥能登の珠洲市で採取される珪藻土は、炭火コンロ用として特に優れています。
金箔工芸品
 金箔工芸品(タジマ)
金箔工芸品(タジマ)
金沢の風土によって生み出された金沢箔は、金沢が世界に誇る伝統の技。
しなやかで美しい光を放つ金・銀箔は、美術工芸品に生かされています。
その他
 福野縞手紡
福野縞手紡
この商品は、富山県南砺市福野で産した木綿織物です。
この「福野縞手紡」は、福野縞の手紡の伝統を知る、ごくわずかな高齢者による手作りの福野縞の商品。